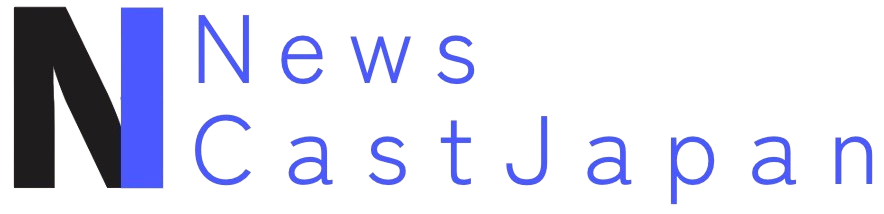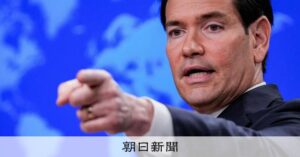【毎日新聞】秩序の解体 見据える中国 トランプ時代の「大国の興亡」
【写真】トランプ政権への失望の声が並ぶ中国米国大使館のアカウント
「米国は一体どうしてしまったのか」「もう一つの大国に似てきた」「世界が100年かけて築いた価値観を破壊しようとしている」
これらは中国大手SNS(ネット交流サービス)にある在中国米国大使館公式アカウントへの書き込みだ。2月末、米国のトランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領と口論を繰り広げた後、失望の声が目に見えて増えた。
もちろん、中国では、競争相手が犯した「敵失」という受け止めが多勢を占める。
◇トランプ流は吉か凶か
米国の威信が低下すれば、世界第2位の経済大国である中国の存在感はおのずと高まる。トランプ氏が侵略者であるロシアに接近し、関税引き上げを強行したことで、米国と西側諸国の間には既に亀裂が生じ始めている。
中国が悲願とする台湾統一への影響も見逃せない。台湾に「米国は信頼できない」との疑念が広がれば、民主主義を信奉する台湾住民の心をくじいて「戦わずして勝つ」ことを目指す中国には願ってもない展開となる。
習近平指導部もこの機会を最大限に生かそうと考えているのだろう。3月上旬に開かれた全国人民代表大会(全人代)では「国際協調」路線をアピールし、米国との差別化を図った。王毅外相は恒例の記者会見で「大国はあるべき態度と責任を持つべきだ」と述べ、新興・途上国などの共感を得ようとしていた。
しかし、「好事魔多し」という言葉があるように、「トランプ流」に潜むリスクに警鐘を鳴らす意見もある。
◇安定壊す「ちゃぶ台返し」警戒
香港中文大(深圳)前海国際事務研究院の鄭永年院長は「国際秩序を維持するコストを不公平と感じるトランプ氏はそれを放棄し、より米国の利益にかなう新たな秩序に作り替えようとしている」と論じている。鄭氏は過去に習国家主席が主宰した専門家座談会で政策提言した経験のある政治学者だ。
鄭氏は「トランプ氏が志向するのは、小国の犠牲をいとわない大国による強者の政治であり、帝国主義の時代への回帰のようだ」と主張し、その象徴がロシアへの急接近だとして警戒心を示した。
「トランプ氏は秩序を覆そうとするいわば造反派だ」と鄭氏は表現した。「造反派」とは、かつて中国を大混乱に陥れた文化大革命の推進者を意味する。自由貿易や国連体制など戦後秩序を利用して台頭してきた中国からすれば、トランプ氏の振る舞いは土壇場での「ちゃぶ台返し」のように思えるのかもしれない。
「中国にとって重要なのは安定だ。米国が秩序維持の役割を放棄することが必ずしも利益にならない」。これが鄭氏の見解であり、「中国が米国に取って代わる準備はまだできていない」との現状認識を示した。
別の識者もトランプ氏が引き起こす混乱に懸念を抱いていた。清華大国際関係研究院の閻学通教授は1月のフォーラムで「巨大な存在である米国の突然の変化はどの国にとっても好ましくない。米国が水を飲み過ぎると我々は干上がるが、水を飲まなくなっても水浸しになってしまう」と指摘。その具体例として、米国のアフガニスタン撤退によって中国の周辺地域が不安定化したことを挙げた。
孤立主義的な米国の動きが中国の勢力拡大につながるとの見方について、閻氏は「米国が『割に合わない』と手を引いた地域に、利益と損失のどちらが残されているのかを見極める必要がある。そこに進出しても負担やトラブルを背負ったり、他国の反感を買ったりする二の舞いになりかねない」と慎重な態度だった。
◇覇権のコスト 誰が担うか
確かに、習指導部の最優先事項は一党支配体制を支える国内経済の立て直しにある。閻氏の発言からうかがえるように、米国の代わりに火中の栗を拾ったり、大盤振る舞いしたりする時期ではないというのが本音のように思える。
トランプ政権が対外援助の凍結を発表したが、中国もまた、経済圏構想「一帯一路」の規模を縮小させている。経済減速に直面する中国が、米国の抜けた穴をどこまで埋めるかは不透明感がある。そもそも一帯一路は投資主体であり、政府開発援助(ODA)と比べて金利などの条件が厳しいという問題もある。
以下全文はソース先で
3/31(月) 10:45 毎日新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/4bc76f4e9689cc3267b8d92336f8f7bea4a30c6a
引用元: ・【毎日新聞】秩序の解体 見据える中国 トランプ時代の「大国の興亡」[3/31] [ばーど★]
日本人は現実を受け入れよう。
The post 【毎日新聞】秩序の解体 見据える中国 トランプ時代の「大国の興亡」 first appeared on TweeterBreakingNews-ツイッ速!.