渡辺 裕(東京大学名誉教授)

<「著作権法上の理由」で教材にモザイク、先行文献の引用が「剽窃」…。この奇妙ながんじがらめを後世の人はどう思うのか? 『アステイオン』101号より「『コンプライアンス』という正論」を転載>【渡辺 裕(東京大学名誉教授)】
もう半年以上も前[編集部注:2024年11月時点]になるが、《不適切にもほどがある!》というテレビドラマが話題になった。
1986年からタイムスリップして現代の日本に来てしまった、「昭和」を絵に描いたような主人公が、両時代の価値観の激しい乖離のなかで巻き起こすトラブルを通して、「コンプライアンス」優先の現代社会の問題点を、宮藤官九郎流のコミカルなタッチで描き出したものだ。
このドラマが大きな反響を呼んだのは、何かにつけ「コンプライアンス」重視の「正論」に振り回されがちな現代社会のあり方に疑問をいだいている人がそれだけ多いということでもあろう。
もちろん、迷惑行為、不公平や差別がまかり通っていた時代を、「昔は大らかで良かった」などと讃美するつもりなどないが、この種の「正論」にどこかおかしいと感じたような体験は誰でも一度や二度はあるだろう。
私自身が最近そんな疑問を感じた事例を2件ほど取り上げてみたい。どちらも著作権に関わる問題である。
ひとつは私自身が最近、ある大学で講演を行った際に体験したことで、講演の映像を大学のウェブサイトで公開するにあたり、講演内で使用した動画や音源、さらには本などの文字テクストの引用までが「著作権上の理由」でほとんど削除されたりモザイクをかけられたりしたという事態である。
著作権法上、他人の著作を勝手に使うことは許されないが、著作権法には例外事項があり、学術的な著作等で自説の補強や他人への論評のために適切な範囲内で引用することは認められている。
今回のケースでは(少なくとも私自身の認識では)いずれも適切な範囲内で典拠も記載して引用しているつもりなのだが、公開された動画ではそのほとんどすべてが削除・モザイクの対象となってしまった。
著者の死後70年以上が経ち、そもそも著作権保護の対象ではない本の引用まですべてモザイク処理になっており、これには驚いてしまった。
どこまでが「適切な範囲内」なのかの具体的な基準が著作権法自体には書かれていないため、線引きのしようがなく、許諾のないものはすべて削除・モザイクの扱いにしたということだったようだが、著作権法があえて具体的な規定を避けたのは、事例ごとのきめ細かい判断の余地を残すためであり、「著作権法上の理由」という「正論」を曖昧に適用し、すべてを一括して削除してしまうのはあまりにも乱暴である。
YouTubeで配信するため、そちらのチェックで引っかかることを怖れたことなどもあろうが、そんな「自己規制」や「忖度」が積み重なり、既成事実化してゆけば、本来認められていた引用というカテゴリー自体が有名無実化することにもなる。
他人の説を批判するための引用にも相手の許諾が必要というようなことになれば、健全な言論活動は阻害されてしまうだろう。
もうひとつの事例も同じく著作権に関わる、こちらは私の友人が巻き込まれた事件である。
大学の出版物に投稿した論文が米国で出版されている先行文献の剽窃とみなされて学内のコンプライアンス委員会に通報され、懲戒解雇処分になってしまったという事案である。この処分を不当として訴訟を起こしたものの、一審の東京地裁では主張が認められず敗訴し、現在東京高裁に控訴して係争中である。
解雇の不当性を争う裁判なので、基本は労働法の案件ではあるが、少なくともこの解雇にいたる事実関係の中心にあるのは著作権問題であり、そこで下された不正という判断は、音楽研究のみならずおよそ人文学の研究に関わる者には由々しき大事である。
というのも、ここで問題とされた先行文献の使い方は、この分野ではかなり普通に行われているものだからである。
もちろん、研究論文はオリジナルなものでなければならず、他人が言っていることと自分の言っていることとはっきり区別し、典拠を示さなければならないというのは、研究のイロハであり、全くもって「正論」には違いない。
※以下引用先で
引用元: ・学術的引用すら許されない「コンプライアンス」が追い詰める「学問の自由」(渡辺裕東京大学名誉教授) [七波羅探題★]
やり直し
引用しかしなかったのアンタら学者だろ
無能な学者を増やし過ぎた弊害の泣き言なんて知らないよ
違法転載してる5ちゃんの記者もすごいな
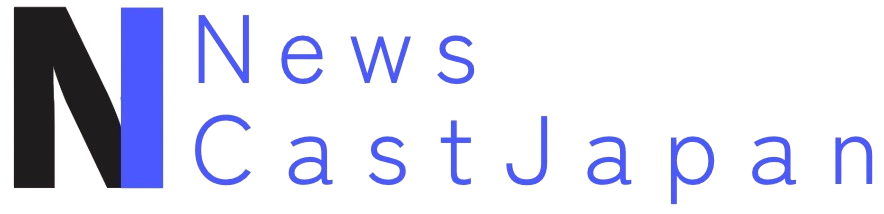







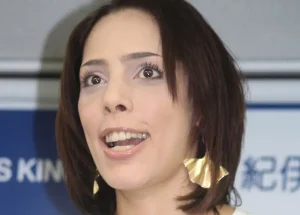

コメント一覧